
日本語には、読み同じでも漢字が違う言葉が沢山あり、時々どちらなのか迷ってしまうことがあります。
「生かす」と「活かす」もそんな言葉の代表的なものと言えますね。
この2つの言葉、意味は似ているようですが、明確にどのように使い分けるか分からないという方も多いのではないでしょうか。
メールだと漢字は変換してくれても、その意味までは教えてくれないのでこういう時に困ってしまいますね。もし目上の方への手紙で使い方を間違っていたらと思うと、ちょっと恥ずかしいですね…。
そこで、「生かす」と「活かす」の違いと、その使い分け方について紹介していきますので、ぜひ参考にしてみて下さいね。
「生かす」と「活かす」の違いは
「生かす」は生き物に関わる言葉
まず「生かす」の意味は次の通りです。
- 命を保たせる、生き長らえさせる。
- 一度途絶えてしまった生命などを、再び蘇らせる。
- 才能や技能などを充分に使う。
生かすのイメージとしては、生命に関わる事柄や生物が持つ能力に関して使う言葉となります。
「活かす」は新聞で使えない?!

一方の「活かす」の意味は次の通りです。
- 物事や事柄が持つ能力を引き出して使う。
- 状況や能力などを有効に使う。
実は意味としては、「生かす」も「活かす」もほぼ同じような意味。違いは「活かす」では生命に関係する使い方をしないこと。
活かすのイメージとしては、現在の立場や状況を役立てて、より良い状況に持ち込むときに使います。
実は「活かす」は「常用漢字の読み方」ではありません。読み方としては間違いではないけれど、一般的な使い方ではないという事です。私的な文章やメールで使う分には問題ないのですが、新聞・公文書では活かすは使われません。
よく注意して新聞を読みますと、たしかに「活かす」と使いたい文章でも「生かす」を使用しています。あるいは言い回しを変えて、「活用する」としている場合もありますね。
ただここまで細かく気を使うのは、新聞社や公的文章を書く人ぐらいです。私達が書く普段の文章では、あまり気にせず「活かし」ましょう。
生かすと活かす、それぞれの使い分け
経験は生かす?活かす?
それでは、「生かす」と「活かす」の具体的な使い分けを、例を出して説明します。
- その経験を「いかす」
この場合は、命にかかわらない物事に対しての「いかす」です。「生かす」でも正解ですが、「活かす」のほうがより伝わります。
- 料理の腕を「いかして」仕事に取り組みたい。
- 素材を「いかして」料理に取り組む。
似ているようで内容の違う文章ですが、この場合は前者が「活かして」、後者が「生かして」がより自然。
前者は技能を活用するという意味で、「いかして」という言葉を使っています。後者はどちらでも当てはまりますが、一般的には「生かす」を使います。味を活用する、というよりは味の生命をよりよくする、といった具合でしょうか。
どちらか迷ったときは、常用漢字の読み方の「生かす」を使えばまず問題ありません。
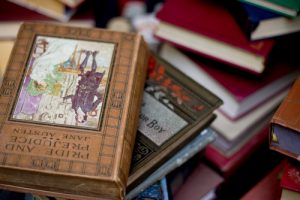
「生かす」はいつ使う?
逆に「生かす」を使うべき文章は、どの様なものがあるでしょうか。
- 釣った魚を水に入れて「いかす」。
- 「いかす」かどうかはお前の返答次第だな!
サスペンスドラマの様な例文になってしまいましたが、いずれも「命」に関わる言葉です。いずれも「活かす」では、文章としてしっくりきませんね。このように命が関わる文章では「生かす」を使いましょう。
関連記事:
- 「寂しい」と「淋しい」の違いとは?どう使い分ける?
- 「充分」と「十分」の違いとは?どう使い分ける?
- 「ずつ」と「づつ」の違いや使い分け!正しいのはどっち?
- 「すいません」と「すみません」の違い、どっちが正しいの?
- 「お疲れ様です」と「お疲れ様でした」の違いって何?どう使い分ける?
- 「おざなり」と「なおざり」の意味と違いとは?どう使い分ける?
命は「生かす」、その状況は「活かす」
生かすと活かすの違いについては、基本的には同じものと考えて大丈夫です。
どちらが正解か迷ったときは、常用漢字として使われる「生かす」を使うと覚えておきましょう。
特に履歴書ですと相手が細かくチェックするため、常用漢字かどうかは気をつけたいですね。実際はそこまで気にしなくても良いかも知れませんが、念には念を入れたほうがより安心です。
調べた知識を「活かして」、今後の生活に「生かせる」ように使い分けましょう!
コメントを残す